
介護ニュース
接遇とは? 人手不足で増える高齢者施設でのクレームの種類と初期対応
良質なサービスを提供し利用者の満足度を維持するために、高齢者施設では適切な接遇とクレーム対応が欠かせません。しかし、慢性的な人手不足が接遇に影響し、利用者や家族からのクレームにつながることも。接遇を向上させることはクレーム予防や人材の流出防止にもつながります。人手不足の中での接遇向上の工夫やクレーム対応のポイントについて考えます。

接遇とは? 介護現場に求められる「対応力」
接客業全般で重視される接遇とは、おもてなしの心を込めて相手に接することです。単に丁寧な言葉遣いや態度を指すのではなく、相手に寄り添い、思いやりを実践する姿勢を意味します。高齢者施設では、スタッフの接遇の質が利用者や家族の満足度に大きく影響し、安心感と信頼関係の構築につながります。接遇には基本となる5原則があります。
- あいさつ・声かけ:相手の目線に合わせ、明るい笑顔で気持ちのよい声かけを
- 言葉づかい:相手に合わせたていねいで不快感のない言葉を選ぶ
- 表情・笑顔:つねににこやかな表情を心がけ、安心感と親しみを印象づける
- 態度:姿勢や立ち振る舞いを整え、傾聴の姿勢を示す
- 身だしなみ:清潔で安全に配慮した服装と身だしなみを保つ
介護現場では利用者一人ひとりに合わせた対応力が必要になりますが、以上の原則を意識した上で、個人によりそった対応を心がけましょう。
よくあるクレームの種類とその傾向

ここまで接遇の基本を確認しましたが、次は実際に利用者や家族から寄せられるクレームの種類について紹介します。
高齢者施設で発生するクレームは「連絡・説明不足」「職員の対応に不満」など、コミュニケーションや感情面に関することに加え、金銭的な不満や疑問が多いようです。クレームはないに越したことはありませんが、クレームには現場の課題が隠れていることが少なくありません。クレームに対処しながら、課題を引き出しサービス改善に役立てたいものです。ここでは、入所型の施設で実際にあった事例を紹介しますので、クレームの内容と解決のためのポイント、引き出された課題をみてみましょう。
事例1)利用者の転倒による骨折に関する家族からのクレーム
<概要と経過>
- 夜間、ベッド脇のセンサーマットが鳴った。スタッフは他の利用者の介助中であったため、数分後に駆けつけると居室内で利用者が転倒していた
- 本人は痛みを訴えなかったが、救急搬送した結果、大腿骨骨折と診断され入院
- 家族から夜間の見守り体制への不満や入院中の介助負担に関する相談があった
<解決へのポイント>
- 事故時には速やかに医療機関へ連携し、家族にも状況を説明
- 家族の意見を傾聴し誠意ある対応を行い、以下を確認・実施:-ナースコール対応の優先順位を職員間で明確化
-入院中の利用者に関しては、病院で可能な範囲で食事や連絡面のサポートを行う
-治療費が医療保険や施設で加入している損害保険で対応可能であることを家族に説明
<今後の課題>
夜間のナースコール対応に関しては、スタッフ体制等の検討が必要
事例2)新人スタッフの対応への不満
<概要と経過>
- 新人スタッフが他の利用者のナースコール対応に向かっている途中、利用者本人から呼ばれたが、気づかずに通りすぎた
- 同スタッフによる介助の際、雑な対応に痛みや不快感があった
- 家族から以上のクレームがあり、謝罪した上で施設としての今後の対応を報告
<解決へのポイント>
- 介助中も周囲の状況確認を徹底する
- 施設内外の研修の参加により、新人の介護スキル向上を図る
<今後の課題>
- 各スタッフの介護スキルの向上、一人ですぐに対応できない場合は応援を仰ぐ
- 利用者の気持ちに寄り添った支援のあり方
事例3)請求書等の金額が間違っていた
<概要と経過>
請求書、領収書の控除対象額が0円となっていて、確定申告が遅れたと家族から連絡があった
<解決へのポイント>
- 謝罪し、ただちに正しい領収書を再発行した
- なぜ、金額が間違っていたのか、原因の特定作業を行う
<今後の課題>
請求書等の発行の際は、事務スタッフに加え、施設内の複数のスタッフで内容をチェックし、誤請求や記載ミスを防ぐ
クレーム増加の背景にある“人手不足”の現実

人手不足の現場では、介護スタッフ一人あたりの負担が増大し、接遇の質が低下しがちになってしまいます。スタッフの時間的、精神的な余裕のなさが利用者への対応に影響することで、小さな不満がクレームに発展することがあります。スタッフが精神的に余裕を持って働ける環境は、接遇の質向上につながり、結果的に働きやすい職場環境となります。
業界全体で人手が不足するなか、働きやすく人材流出の少ない職場づくりを目指すには、業務負担を改善するサポート体制が必要です。
そこで、期待されているのがデジタル化による業務の効率化です。例えば、見守りカメラと連動したナースコールシステムを導入すれば、スタッフの負担が大きい見守りや巡回業務を大幅に効率化できます。「Vi-nurse見守り映像システム」は、遠隔で利用者の様子を映像で確認することができるので、駆けつけの必要性やコール対応の優先順位を即時に判断することが可能になります。これなら、特に負担の大きい夜間の見守り業務も改善でき、スタッフに余裕が生まれ人材流出の防止にもつながるでしょう。
また、「Vi-nurse見守り映像システム」には録画機能もあるので、転倒事故などの際、状況の確認と共有ができ、クレーム対応や今後の事故防止対策の検討にも役立ちます。
初期対応の基本とチームでの共有体制

クレームには早急に対処することが欠かせません。時間が経つほどに利用者や家族の不満、不安は大きくなっていくからです。初期の段階ではまず相手の話をしっかりと聴く姿勢が重要ですが、事案の発生もしくは報告があってから24時間以内に初期対応(ファーストレスポンス)を行うようにしましょう。初期対応では、以下のポイントが重要になります。
- 発生した事象に対し謝罪する
- 問題を放置せず対応することを宣言する
- いつまでに対処するのか明確にする
- 状況によっては解決に時間がかかる旨、了承を得る
その後、施設全体で情報を共有し、再発防止策を迅速に講じることが信頼回復の第一歩です。利用者が不満を抱えていても声に出されなければ、事業者やスタッフは気づけず、改善や解決も進みません。したがって、クレームは現場の課題を解決させるチャンスと前向きにとらえ、接遇の向上に活かすようにしましょう。
クレーム対応と予防には組織で動く仕組みづくりが求められますが、スタッフみんなで意識を高め、日ごろの会話に気を配ったり、満足度のアンケート調査を行うなど、利用者と家族の声をきく機会を設けるのもいいでしょう。そうすることで、長期にわたっての信頼関係を築くことができます。



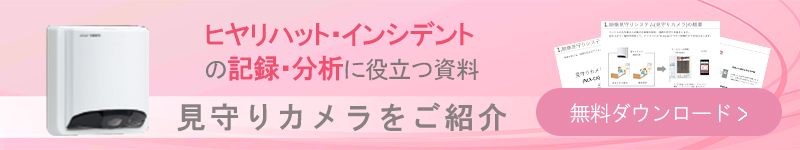
 コロナ5類移行による介護施設、介護現場への影響は? マスク着用はどうなる?
コロナ5類移行による介護施設、介護現場への影響は? マスク着用はどうなる?  地域での暮らしを支える新制度「介護予防・日常生活支援総合事業」とは
地域での暮らしを支える新制度「介護予防・日常生活支援総合事業」とは  withコロナ時代で加速する介護ロボット導入の補助金最新情報
withコロナ時代で加速する介護ロボット導入の補助金最新情報